
クオリティフォーラム2017 企画セッションとsて「進化する自工程完結~自工程完結に学ぶホワイトカラーの業務品質向上~」 をテーマにパネルディスカッションレポートが行われた。
<パネリスト>
佐々木眞一氏
トヨタ自動車株式会社 顧問・技監
大塚万紀子氏
株式会社ワーク・ライフバランス パートナー・コンサルタント
山中恭一氏
イビデン株式会社 理事 生産推進本部副本部長 兼 CSR推進室長
<コーディネーター>
森浩三氏
一般社団法人 中部品質管理協会講師 秋田県自動車産業アドバイザー
――――――――――――――――――――――――――――――――
本講演は、日本科学技術連盟主催の、「クオリティフォーラム2017」
における講演内容をまとめたものです。
――――――――――――――――――――――――――――――――
佐々木眞一氏
トヨタ自動車株式会社 顧問・技監
大塚万紀子氏
株式会社ワーク・ライフバランス パートナー・コンサルタント
山中恭一氏
イビデン株式会社 理事 生産推進本部副本部長 兼 CSR推進室長
<コーディネーター>
森浩三氏
一般社団法人 中部品質管理協会講師 秋田県自動車産業アドバイザー
――――――――――――――――――――――――――――――――
本講演は、日本科学技術連盟主催の、「クオリティフォーラム2017」
における講演内容をまとめたものです。
――――――――――――――――――――――――――――――――
森氏:まず、3人の講演者それぞれの講演内容を確認したうえで、4つの切り口を提示したいと思います。
佐々木さんの講演では、ホワイトカラーの生産性向上が課題であると問題提起がされました。そのうえで、ホワイトカラー労働は一つひとつの意思決定のつながりであること、そのため、生産性向上のうえでは、プロセス志向の仕事の進め方を普及していかなければならないことについて、お話しいただきました。
大塚さんの講演では、時間の制約下で仕事の仕方の改善を促すことがポイントであることが強調されました。さらに、上司と部下、個人とチームのコミュニケーションを活性化させ、日々の業務改善を積み重ねていくことが重要だと述べられました。具体的には、日々の作業と所要時間を、朝と夕方のメールを使い、before & afterで毎日検証しながら問題を見出し、そのなかに改善の課題を見出し、改善していく方法が紹介されました。
山中さんの講演では、イビデン社の取り組みについて紹介されました。同社では、2016年から自工程完結の取り組みを本格化させ、社長、全役員の理解のもと、全社運動を巻き起こしているのがポイントです。さらに、直近の成果を追求するのではなく、取り組みを重視し、日常業務における小さな改善の積み重ねに価値を見出すところが重要である旨が述べられました。また、「目的・目標・アウトプット(MMO)」が、上司と部下における日常のコミュニケーションのキーワードになっている点が紹介されました。仕事を始めたり、仕事ができたかどうかチェックしたりするときに、MMOの軸がぶれないよう浸透させていると言います。そのほか、「遅くとも19時には帰りましょう」という運動を、日常業務改善の動きと連動させて行っていることが紹介されました。
以上を踏まえたうえで、以下の4つの切り口を設定したいと思います。
1.生産性向上のうえでは、「時間制約が先か、業務改善が先か」、という切り口。因みにワーク・ライフバランス社やイビデン社の取り組みでは時間制約が先でした。
2.コミュニケーションの在り方に関する切り口。上司と部下に限らず、担当者とチームメンバー、担当者と顧客・後工程のあいだで、うわべではない、実のあるコミュニケーションを行うことが仕事の質を向上させる、ということについて考えたいと思います。
3.小さな改善の積み重ねに関する切り口。日々の改善をいかに評価し、大きなうねりにつなげていけるかがポイントになるかと思います。
4.トップマネジメント層の意識改革についての切り口。大塚さんの講演にあった、人口オーナス期において経済発展するルールに乗り換える意思決定は、トップがしていかないといけないところだと思います。
佐々木さんの講演では、ホワイトカラーの生産性向上が課題であると問題提起がされました。そのうえで、ホワイトカラー労働は一つひとつの意思決定のつながりであること、そのため、生産性向上のうえでは、プロセス志向の仕事の進め方を普及していかなければならないことについて、お話しいただきました。
大塚さんの講演では、時間の制約下で仕事の仕方の改善を促すことがポイントであることが強調されました。さらに、上司と部下、個人とチームのコミュニケーションを活性化させ、日々の業務改善を積み重ねていくことが重要だと述べられました。具体的には、日々の作業と所要時間を、朝と夕方のメールを使い、before & afterで毎日検証しながら問題を見出し、そのなかに改善の課題を見出し、改善していく方法が紹介されました。
山中さんの講演では、イビデン社の取り組みについて紹介されました。同社では、2016年から自工程完結の取り組みを本格化させ、社長、全役員の理解のもと、全社運動を巻き起こしているのがポイントです。さらに、直近の成果を追求するのではなく、取り組みを重視し、日常業務における小さな改善の積み重ねに価値を見出すところが重要である旨が述べられました。また、「目的・目標・アウトプット(MMO)」が、上司と部下における日常のコミュニケーションのキーワードになっている点が紹介されました。仕事を始めたり、仕事ができたかどうかチェックしたりするときに、MMOの軸がぶれないよう浸透させていると言います。そのほか、「遅くとも19時には帰りましょう」という運動を、日常業務改善の動きと連動させて行っていることが紹介されました。
以上を踏まえたうえで、以下の4つの切り口を設定したいと思います。
1.生産性向上のうえでは、「時間制約が先か、業務改善が先か」、という切り口。因みにワーク・ライフバランス社やイビデン社の取り組みでは時間制約が先でした。
2.コミュニケーションの在り方に関する切り口。上司と部下に限らず、担当者とチームメンバー、担当者と顧客・後工程のあいだで、うわべではない、実のあるコミュニケーションを行うことが仕事の質を向上させる、ということについて考えたいと思います。
3.小さな改善の積み重ねに関する切り口。日々の改善をいかに評価し、大きなうねりにつなげていけるかがポイントになるかと思います。
4.トップマネジメント層の意識改革についての切り口。大塚さんの講演にあった、人口オーナス期において経済発展するルールに乗り換える意思決定は、トップがしていかないといけないところだと思います。
時間制約は業務改善の目標になる

大塚氏:難しい問題ですが、私自身の経験からすると、時間制約が業務改善の目標になるのではないかと思います。時間制約や、山中さんのおっしゃるMMOがあると、そこから、「日々の業務の工夫をしていこう」という思考が働いていくのではないでしょうか。逆に「業務改善せよ」と先に言われても、何を目的にして、何時間労働時間を減らしたいのかが見えないと、なかなか効果的な取り組みは出てこないように感じます。
佐々木氏:業務改善の手法を広めている立場からすると、業務改善ありきだと言いたいところはありますが、私も経験から言うと、「業務改善を先に行って効率化をしよう」というやり方は、案外成果が出ないように感じられます。やはり、人間は何か目的意識が働かないと、いくらいい知恵を持っていても、それを使う気にならないものだと思います。また、トヨタ社で実際に行ったことのある事例ですが、1分で1台車ができてくるラインを、チャレンジとして58秒に縮めて回したことがあります。すると、どこかの工程が「もう間に合わない」と手を挙げます。そこが改善すべき一番手であることがわかる仕組みです。このように、問題を顕在化させるための指標としても、時間制約は有効だと思います。
森氏:イビデン社の「19時に帰りましょう」の運動は、まさに業務改善に先立つ時間制約だと思います。現在はどのような位置づけになっているのでしょうか。
山中氏:定時である17時の10分前に、「19時に帰りましょう」の放送が流れます。毎日放送を流すことで、意識を持たせるようにするという位置づけです。そのほか、弊社では、さまざまな業務や活動の目標期限について、上司と部下で共有するようにしています。計画どおりにいかないことも多いですが、うまくいかなかったことに対して、次はどうするのかという議論が、少しずつ出てくるようになってきたように感じています。
森氏:自工程完結においては、プロセス志向で仕事を進めることが求められています。やるべきことを明確化し、それを一つひとつ確実に踏んでいくということです。先ほどまでの話にあったように、時間制約を先に持ってくることによって、差し迫った状況に置かれ、知恵が出てきて、業務改善が進むという考えはひとつあります。しかし、一方で、時間制約を先に持ってきてしまうと、やるべきことではなく、やれる範囲のことだけをやって終わってしまうのではないかという懸念もあるでしょう。この点について、会場からご意見をいただけませんでしょうか。
会場の参加者:時間短縮を最初に持ってきたとしても、今やっている仕事の意義や目的がきちんと伝わっていれば、心配ないと思います。
コミュニケーションによる良好な関係性の構築が生産性向上のカギ
森氏:続いて、「コミュニケーションの在り方」の切り口について、それぞれご意見をお願いします。大塚氏:私たちがコミュニケーションを大切にする理由として、マサチューセッツ工科大学で組織論を研究しているダニエル・キム氏の提唱する「組織の成功循環モデル」があります。この理論では、組織における結果の質を高めたい際、結果の質にこだわりすぎると、バッドサイクルに入ってしまうことが指摘されています。結果の質にこだわりすぎると、指示命令型の組織になってしまうためです。従業員が言われたことしかやらないなど、自発性が失われたり、反発が生まれたりしてしまいます。
ここで重要なのは、関係の質です。チームの中で互いにコミュニケーションを取りながら、それぞれが考えていることについて会話を続けることで、思考の質が変わります。そして思考の質がポジティブに変わっていくと行動の質が変わっていき、そのことで結果の質が変わるという正のサイクルです。ゴールは生産性向上にありますが、足元では、チーム・組織の中におけるコミュニケーションの活性化と、それによる信頼関係の構築を行っていくのが理想だと考えます。
森氏:W・エドワーズ・デミング氏の指導では、「結果を求めるな」ということが繰り返し言われてきていますが、それと似たようなことなのでしょうか。
大塚氏:ビジネスですので、最終的には、結果を求めていきたい心理はあるでしょう。ただし、焦りは禁物だと思います。管理監督者・経営者は、きちんと仕事を認める声掛けをしたり、多様性を理解したりすることが、関係性の質向上につながると思います。
佐々木氏:コミュニケーションには2つのポイントがあると考えます。ひとつは論理性を求めること。組織では、その内部でしか通じない、ある種の「方言」のようなものがはびこることがありますが、そうなってしまうと、その言語体系のなかでの発想しかできず、コミュニケーションが広がりません。したがって、論理性・言葉の正確性を意識する必要があります。
もうひとつは、養老孟司氏の言う「会話における脳内方程式」の論理で説明できます。会話における脳内方程式は、「y=ax」で表すことができると言います。yは理解度、aは会話をする人同士の関係性、xはどのくらい丁寧に説明するかです。ここでポイントになるのはaの値で、プラスマイナス無限大から0(ゼロ)までの幅があります。a=0のときは、こちらがいくら丁寧に説明しても相手は無反応で、理解は0(ゼロ)しかない状態です。一方、a=無限大は、ある意味での原理主義です。「相手の言うことは、何があっても絶対」という考え方になり、これも問題があります。理想は、a=1の状態です。その関係性をどう構築するかが重要になってくると思います。
山中氏:弊社では、毎朝、ツールボックスミーティングを義務付けています。また、ラインもスタッフも、日報を欠かさずつけています。これらの取り組みには、体調が悪い人などを確認する目的もありますが、その日の仕事や悩み事などについて会話をする、ひとつのきっかけになると考えています。
森氏:コミュニケーションと言うと、うわべの接触として理解しがちな部分もあるかと思います。仕事の質を上げていこうとするとき、コミュニケーションで発せられる言葉をどう選ぶかが重要になるでしょう。たとえば、トヨタ社には「なぜ」という文化がありますが、この「なぜ」も、重要なコミュニケーションのキーワードだと考えます。相手の言うことを鵜呑みにせず、その理由、背景、原因を知って発言しているのかを問うことが、コミュニケーションを広げていくのではないでしょうか。
小さな改善の積み重ねが組織の生産性を向上させ、イノベーションを起こす
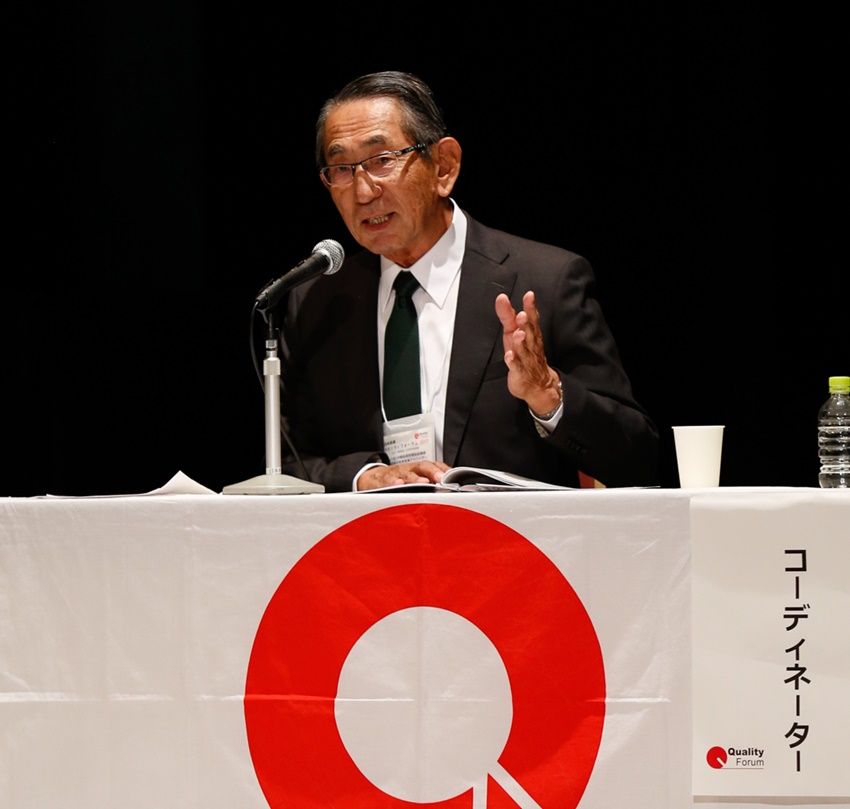
大塚氏:朝メール・夜メールは弊社でも行っていますが、定期的に集計ができ、ある程度まとまった段階で振り返る際に、一日一日の仕事が正しい情報であるところにメリットがあると思っています。また、日々の積み重ねがあるからこそ、「一気に半減しよう」ではなく、「ひとまず3%ずつ減らしてみよう」という議論ができるのも利点です。スモールゴールを設定できれば、ちょっとした背伸びで成功体験が積め、それが次の改善への加速に繋がっていくと感じています。
もうひとつ、小さな積み重ねの例を紹介しますと、ある企業では、朝メール・夜メールで、役員会の資料作成に数千万円の費用がかかっていたことが明らかになったと言います。それを相談することで、資料の枚数上限を決めたり、数字表記を統一したりなどの改善が行えて、結果、大幅な費用削減を実現させたそうです。
森氏:イビデンの取り組みである「“自”工程完結」の表記において、“自”が強調されているのは、「一人ひとりが全員」という、小さな積み重ねを狙いとしているのでしょうか。
山中氏:そのとおりです。弊社にも会社目標や組織目標は当然あり、それを達成するための活動もありますが、“自”工程完結の取り組みでは、そうではなく、一人ひとりの困りごと・モヤモヤを解決することを重視しています。当初、トップには「そんなことをして何になるのか」という思いもありました。しかし、部下の顔色が変わり、はきはきしてくるのがわかってきます。指標として客観的には見えづらいですが、会社がよくなってきていることがじわじわ実感できてきているのではないかと思います。
佐々木氏:小さな積み重ねは、イノベーションともかかわっていると考えます。イノベーションを起こすためには、その前段階として、現状における改善をやりつくしたという状況になる必要があります。そうした改善をやりつくすためには、小さな改善を積み重ねるしかありません。ひらめきでイノベーションを達成できる人もいますが、そうした人の登場を期待しているだけでは、企業は活動できないでしょう。小さな改善を突き詰めた先に、凡人が起こせる大きなイノベーションが待っていると思っています。
森氏:自工程完結の「自」には「おのずと」結果が出るという意味合いもあると考えます。おのずと結果が出るような理想状態に近づけるためには、適切な問題設定が必要です。自工程完結で重要なのは、プロセスの見方だと考えます。そのプロセスについても、やるべきことの順番にとどまらず、さまざまな部署とタイミングを合わせて情報をやり取りすることが必要でしょう。タイミングが合わなければ情報が欠落したり、誤った情報で仕事をしてしまったりして、結果としてミスにつながります。やるべきことがわかっていたとしても、「何がなければその作業ができないのか」という良品条件の見方がなければ、適切にプロセスを遂行できません。その見方がわかってくると、今まで気づかなかったところに問題が見えてくるのではないでしょうか。
働き方改革実践のためには、トップのリーダーシップが必要

大塚氏:弊社では、ワーク・ライフバランスの取り組みをする際には、必ずトップと戦略を練りますし、トップだけを集めて必要性を討議することもあります。そのときに必ず伝えるのが、「まず、トップがワーク・ライフバランスをとってください」ということです。トップ自らが背中を見せてくれることが重要であるためです。
人口ボーナス期型のルールからオーナス期側のルールに飛び移るとき、後者は目の前に見えてはいますが、実際飛び移るのにはしり込みする人が大半です。そんななか、「うちの会社のトップは飛び越えたんだ」と従業員が感じれば、従業員自身もワーク・ライフバランスに取り組もうという意識が芽生えると思います。意識改革だけでなく、行動を起こして、新しいワークスタイルや価値創造に対する姿勢を見せるよう、そのようにトップにはお願いしています。
森氏:イビデン社では、自工程完結の取り組みを行うことについて、事務局から社長を説得したのでしょうか、それとも、社長のリーダーシップによって始めたのでしょうか。
山中氏:最初から社長は、「働き方改革」につながる取り組みとして“自”工程完結を浸透させたいという想いがありました。社員一人ひとりのモチベーションアップが社長の狙いで、それと日常での自工程完結の取組み方がぴったりはまったのが大きかったと思います。
自工程完結によるホワイトカラーの生産性向上には、評価軸の客観化が重要
森氏:最後に、全体を通じてコメントをいただけませんでしょうか。佐々木氏:ホワイトカラーにおける生産性向上をやっていく中で難しさは、アウトプットの評価軸にあると思います。ライン業務には原単位があるため、生産性について論理的に評価できます。一方、ホワイトカラーの仕事は、評価の個人差が大きい。だから、これまでは残業時間など、「時間」という誰から見てもわかる単位でアピールしていたところが大きいでしょう。これからは、大塚さんのお話にあった「朝メール・夜メール」などでデータを蓄積し、アウトプットの相場観をそれぞれの組織で作り上げていくことが、生産性を上げるために重要になるのではないでしょうか。
大塚氏:働き方を変える際には、その先にある、いい未来を意識することが大切だと思います。働き方を変える目的については、危機感だけでなく、「こういう仕事の仕方ができたら楽しい」というポジティブなところを語り合うところからスタートするのがよいのではないでしょうか。さまざまな社会状況の変化やそれに伴う困難はありますが、仕事で価値を出すことの楽しみが重要だと考えます。
山中氏:弊社におけるGood JC活動は、まだスタートしたばかりです。自工程完結の考え方は、頭では理解できるが、それを行動に移すことは難しいと実感しています。トップになればなるほど、業績重視の考え方になり、社員一人ひとりにおける困りごとの優先順位が下がってしまうのが課題です。そこを長い目で見て変えていく必要があると考えています。
森氏:もともとトヨタが始めた自工程完結は、「失敗しない仕事の仕方を追求しよう」という考え方です。失敗しなければ、結果的に手戻りがなく、生産性向上につながります。今回の講演とパネルディスカッションでは、そうした「失敗しない」と言い切れる仕事の仕方を追求する自工程完結こそが、ホワイトカラーの生産性向上に結び付く、という道筋を確かめられたのではないでしょうか。


















